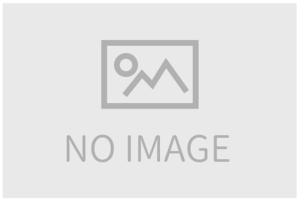箱根へ挑んだ筑波大100年の系譜(1)
草創期の東京高師時代
マラソンは孤独でつらい競技だ。単調な長距離レースをチーム競技に仕立てて各校で競い合えば、対校意識も生まれて練習にも熱が入るのではないか。五輪のマラソンで屈辱を味わった金栗四三が考案した壮大なレースは実現したものの、長距離選手10人がそろうチームは少なく、参加したのは早稲田、慶応義塾、明治と金栗の母校、東京高等師範の4校。記念すべき第1回大会が開かれたのは1920年(大正9年)2月のことだった。
当初は紀元節(現在の建国記念の日)の11日が初日だったが、東京市電のストライキが予定されており、学生は紀元節の式典へ出席することになっていたため14日に変更。各校とも午前中は授業に出て、スタートは午後1時だったという。いかにものどかな風情だが、始まったばかりの大会でもあり、勉学が本分の当時の学生としては当然の運営だったらしい。
⒋校の第1走者は当時のニューモード、丸首シャツ(Tシャツ)にコハゼで止める足袋(別名:金栗足袋)で身を固め、早稲田はえび茶、慶応は青、明治は紫紺、高師は黄色のたすきを掛けていた。高師の1区は山下馬之助。主催の有楽町・報知新聞社前をスタート、沿道のまばらな声援を受けて快調に飛ばし、品川を過ぎる頃には後続を引き離した。
鶴見の中継所では2位の明治に3分の差を付け、1時間25分0秒で栄えある初代1区の区間賞に輝いた。しかし、2区では明治に抜かれて2位へ後退。5区・小田原で首位の明治がたすきを受けたのは午後6時半ごろで、すでにとっぷりと暮れていた。
箱根山中では地元青年団がかがり火を持って迎えてくれた。山には手負いのイノシシがでるため、要所に猟銃を持った地元民が立って選手が通過するたびに発砲する。銃声が山々に響き渡り、銃口から火を噴くのが木の間隠れに見える劇的な光景だったという。
明治が8時30分36秒に芦ノ湖のゴールに到着したのに続き、高師・大浦留市が2位でフィニッシュしたのは8時38分03秒だった。最下位の慶応が芦ノ湖畔にたどり着いたのは10時に近い夜更けだった。
前夜からの雪が翌朝は数㌢の積雪に。当時の箱根路は近道や抜け道が随所にあり、各校が下見で探した近道を走っても良いという決まりだったが、近道をしても足跡でばれてしまうので各校とも下見の成果が生かせなかったという。金栗ら役員は車で後を追う予定だったが、寒さでエンジンが凍結して動かなくなり、間道伝いに雪道を何度も転びながら小涌谷まで走り、ようやく電車で小田原までたどり着き、そこからは車でゴールへ向かったという。
往路も明治が快調にトップを走ったが、高師は8区の赤塚勝次が区間賞で追い上げ、12分30秒差でたすきを受けたアンカー茂木善作も力走する。品川ではその差を5分にまで縮め、新橋付近でついに明治を逆転。大歓声の中、15時間05分16秒で堂々とテープを切った。2位の明治とは25秒差。早稲田が約10分遅れで3位、16時間50分56秒と大きく遅れた慶応が最下位の4位でフィニッシュし、世紀の大レースは終了した。
自らが提唱した大会に母校が優勝で応え、沿道の声援も予想を上回る大きさだった。大会は大成功で、審判長を務めた金栗の喜びは大きかった。チームの面々は熱狂した校友に囲まれて母校へ凱旋。その夜は「桐花寮」の食堂で大祝賀会が催され、健闘をたたえられた。

第1回大会優勝後に金栗四三(前列中央の黒学生服姿)を囲んで写真に収まる高師チーム
ともに区間賞に輝いた5区の大浦と10区の茂木は同年のアントワープ五輪へ日本代表(大浦は5000m、10000m;茂木はマラソン)として出場した。総合4位だった25年の6回大会の2区を務めたのは、前年のパリ五輪400m、800m、十種競技代表の納戸徳重。10チーム中5位の成績で2位に順位を上げ、往路3位の好成績に貢献した。
高師は翌年から2位、2位、5位、2位、4位と上位争いしたが、ブランク2年を挟んで5位、6位と順位を落とし、30年の11回大会からは文理大として出場することになる。
上位常連の文理大時代
11回大会も6位だったが、その後は浮上できないまま。ようやく38年の19回大会は3位に躍進する。1区で常松喬が区間賞の滑り出しで往路は4位。復路も5位にまとめる安定した運びだった。続く20回大会も4位、21回大会は6年間で優勝5回の日大に続く2位と奮戦。2区で勝亦清政、8区で岡田正美が区間賞を奪うなど、太平洋戦争の中断期前にひときわ輝くレースだった。
茗荷谷の本学に近い護国寺周辺は格好の練習場だった。250mほどの急坂を都電と競走して20~30本、都電に負けたら1本追加になった。地元の大塚には、金栗とマラソン足袋を研究・開発していた黒坂辛作の「播磨屋足袋店」があり、最新の「金栗足袋」提供など、何くれとなく支援してくれたという。
黒坂はのちにランニングシューズを製造・販売する「ハリヤマシューズ」を立ち上げ、大塚を本社に新潟・六日町などに製造工場を展開。ヒールにカップを入れる、インソールを敷く、アッパーをメッシュにするなど最先端の研究と工夫から生まれた「ニューカナグリ」はランナーたちの支持を集めた。しかし、1964年東京五輪の円谷幸吉、68年メキシコ五輪の君原健二らが履いて評価を高めた「オニツカタイガー」(現アシックス)の「マジックランナー」にその座を奪われ、21世紀を前に「ハリマヤシューズ」は姿を消す。
21回大会の3区を走った高橋進は地元広島の高校教員を経て八幡製鉄入り。日本選手権の3000m障害で9連覇を果たしたほか、アジア大会2連覇、52年ヘルシンキ五輪代表にもなった。キャリア晩年は駅伝を中心に40歳まで現役を続け、指導者に転じてからは豊富な経験と科学的トレーニングを融合させてマラソンの練習方法、理論を確立した。メキシコ五輪マラソン銀メダルの君原健二など多くの選手・指導者を育成。国内だけでなく、バルセロナ五輪金メダリストの黄永祚ら韓国マラソン界強化にも多大な貢献をした。