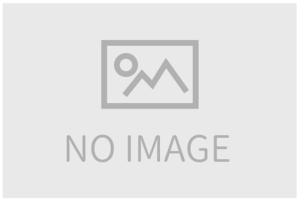エッセー(1)頑張るこころと頑張れるからだ
体力を測る時、暗黙の了解として“全力を出し切る”ことが求められる。
しかし本当に全力を出し切っているかを確かめる手立てはない。
ここ数年モンゴルへ出かけ子どもたちの体力を測定している。
旧ソ連からの独立後急激に社会変革が進行し、社会や生活が大きく変貌をとげている。
変わる社会の変化を直接受け敏感に反応する子どもの形態・体力を追跡調査するのに意義を感じている。
そこで見えてきたのは、社会変動の恩恵を受けた首都ウランバートル(都会)子どもの大きな形態に比較して、昔ながらのゲルの生活を続けている遊牧民の子どもは形態的には劣るが、筋力やスピードなどの総合的体力はほぼ等しい。
主観的ではあるが、田舎の子どもの測定の際の未経験の動作に挑戦する意欲や頑張ろうとする精神的集中力が都会の子どもとの形態的差をカバーしているのではないか、と思える。
そして、改めて“最大努力をする”とは何かを考えさせられた。

かつて猪飼(元東大教授)と矢部(名大名誉教授)は次のような実験を行った。
手の母指内転筋を支配する前腕の尺骨神経に50ボルトの電流を流すと(他の指を支配する神経と異なるため他の指は働かないが、念のため石膏で固めている)被験者の意志と無関係に母指内転筋が収縮し筋力を発揮する。
電気刺激を与えて発揮される最大筋力(生理的筋力)は自発的に発揮される最大筋力(精神的限界)よりも平均約31%大きい値であった。
さらに筆者が精査すると被験者(10名)によって18%~48%と大きな幅があった。すなわち、頑張るこころと頑張れるからだに個人差が顕著であることが分かった。
猪飼は生理的限界のメカニズムを、「ヒトは平常“こころの殻”という内制止(抑制)が本来の自由を奪っているが、外部からの気合いやかけごえ等の外制止が内制止に作用し脱制止を引き起こすことによって、内制止が一時的に消退したものである。すなわち、大脳の運動野に対する抑制的作用が外制止によって一時的に中断することによる」、と説明している。これは同時に、“火事場の馬鹿力”のメカニズムをも説明するものであろう。
普段は抑制がかかっているため生理的限界まで力を出すことが困難であるが、外的環境やあるいは個人の強い意志によって生理的限界値近くまで力を発揮することが可能であることを示唆している。
恐らく、厳しいトレーニングによって自発的最大筋力を限りなく生理的限界まで近づけることができるであろう。
また、筆者の現実的な姿はこれに逆行して、加齢に伴って生理的限界が限りなく心理的限界に近づき、少し頑張ると筋肉に異常をきたすという状況を説明してくれてもいる。

もう10年近くになるであろうか、米国でベストセラーになった一冊の本がある。
それを野中女史が翻訳して『脳を鍛えるには運動しかない!』の刺激的なタイトルをつけ出版している。
それは、イリノイ州ネーパーヴィルの中・高等校へ一人の体育教師が赴任してから学校が大きく変わった話である。
その教師の体育授業の特徴は、楽な楽しいことに流れる現代的生徒に対して、心拍計をからだに付け比較的高強度の運動(80~90%HRmax)を20~30分間頑張って走らせる厳しい授業を課したことにある。
しばらくすると生徒たちが今まで味わったことのない達成感や爽快感、あるいは充実感や効力感(充実感)を体験するようになった。
その頃になると生徒の姿勢や行動にも変化が現れ、こころとからだに自信が芽生え、苦しいことにも積極的にも立ち向かう勇気、体力、忍耐力が強化され、物事を自発的・積極的に行おうとするエネルギーが高まってきた。
その結果、肥満が米国の子どもの平均30%に対してわずかに3%まで減少し、かつて平凡な学校が全米有数の優秀校にのし上がったのである。
この訳本のタイトル“脳を鍛える”とは、“こころを鍛える”ことであり、高強度のランニングを比較的長い時間頑張ることによってからだの鍛錬にとどまらずこころの強化にまで好影響を与えた事例を紹介したものである。(これはあくまで成功した事例であろう)
17世紀にデカルトが『動物機械論』の中で“心身二元論”を唱えた。その後、西洋の生命科学は人間のこころとからだを分離することによって、すなわち、生命の物質的側面が限りなく究明されてきた.(例えば、世界の運動生理学の祖とうたわれたイギリスのAV Hillは1927年に『生命機械論』を発表している。)はたして、人間のこころを度外視した“精密機械論”だけで人間の生命やスポーツ活動を論ずることができるであろうか?
改めて思う。頑張るこころと頑張れるからだは表裏一体をなすと。